こんにちは庵禅逸人(あんぜん いつと)です。
11月といえば「七五三(しちごさん)」の季節です。
着物を着た子どもたちが神社を訪れる姿を見かけると、どこかあたたかい気持ちになりませんか?
この記事では、七五三の意味や由来、そして子どもの健やかな成長を願う「祈りの形」について、わかりやすくご紹介します。
七五三とは?
七五三は、3歳・5歳・7歳の節目を迎えた子どもの成長を祝う行事です。
昔の日本では、今よりも子どもが無事に成長することが難しい時代でした。
だからこそ、「ここまで元気に育ってくれてありがとう」という感謝と、「これからも健やかに成長しますように」という願いを込めて、神社でお祈りをしたのが始まりです。
七五三の由来
七五三の起源は、平安時代までさかのぼります。
当時の貴族たちは、子どもの成長に合わせていくつかの儀式を行っていました。
- 3歳:「髪置(かみおき)」
それまで剃っていた髪を伸ばし始める儀式。 - 5歳:「袴着(はかまぎ)」
男の子が初めて袴をはく儀式。 - 7歳:「帯解(おびとき)」
女の子が帯を結び始める儀式。
これらが一つになり、現在の七五三という形になりました。
つまり、七五三は「命の節目を祝う日本の伝統行事」なんですね。
七五三の時期とお参りの日
七五三は11月15日が正式な日ですが、最近では家族の予定に合わせて、10月〜11月の土日祝日にお参りする家庭も多いです。
また、六曜(大安・友引など)を気にするご家庭もありますが、本来は「感謝と祈りの気持ち」があれば、どの日に行っても問題ありません。
お参りの流れとマナー
七五三では、神社に参拝して「ご祈祷(きとう)」を受けるのが一般的です。
- 神社に事前予約をする
- 受付で祈祷料を納める(5,000〜10,000円が目安)
- ご祈祷を受け、記念撮影
服装は、子どもは着物・袴、親はフォーマルな装いが一般的です。
とはいえ、最近は洋装でも問題ありません。
神様に「感謝を伝える姿勢」が大切です。
七五三に込められた「祈り」
七五三は単なるイベントではなく、「子どもの命に感謝し、これからの幸せを祈る日」です。
昔から日本では、“言葉には力が宿る”と考えられてきました。
だからこそ、神社では静かにこう祈るのがおすすめです。
「これからも健康で、笑顔の多い日々を過ごせますように」
この一言で十分です。
難しい言葉よりも、親の素直な気持ちこそが祈りになります。
千歳飴の意味
七五三といえば「千歳飴(ちとせあめ)」も欠かせません。
長く細い形には「長寿と健康」の願いが込められています。
また、紅白の色は「めでたさと魔除け」を表しています。
子どもが飴を持って嬉しそうに笑う姿には、いつの時代も変わりません。
七五三をもっと特別な日にするために
写真館での記念撮影や家族での会食など、お祝いの形は人それぞれです。
大切なのは「無事に育ってくれてありがとう」という想いを伝えること。
この日をきっかけに、家族の絆を感じる時間を作ってみてください。
まとめ
七五三は、古くから続く「命への感謝」と「未来への祈り」の行事です。
忙しい毎日だからこそ、この日だけはゆっくりと家族の時間を過ごしてみてください。
きっと、子どもにとっても忘れられない思い出になります。

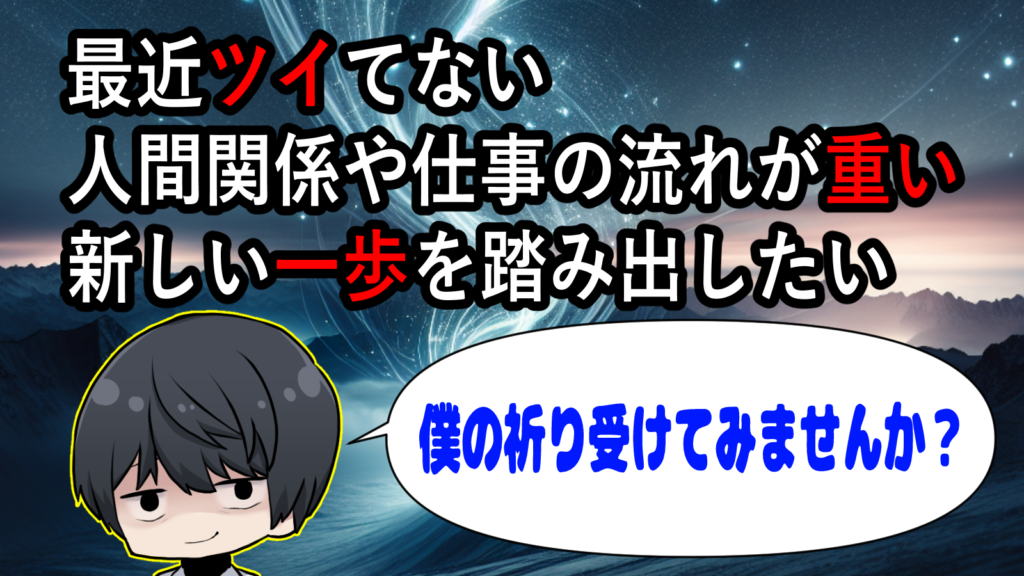
コメント